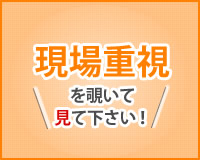2025年8月1日
26. 社会人としての生き方
8月に入りました。連日の猛暑にお疲れのことと存じます。先月は国政選挙がありましたが、与党陣営は大きく議席数
を減らしました。経済の問題、外国人の問題など政治的不信感の高まりが表出化した結果といえるでしょう。
さて今回のテーマは「社会人としての生き方」です。前社長は2015年掲載の第28回:社会人としての生き方にお
いて、「挨拶、返事、時間厳守、身だしなみ」について解説しています。私も読み返して納得した中で、“挨拶”につ
いて調べてみました。
挨拶には、声掛け、会釈、お辞儀、握手、ハグなど様々な形式があります。この中で、お辞儀が中国から日本へ伝
わったのは、仏教が広まった500年から800年頃のことと言われており、お辞儀は相手へ頭を下げて首を見せる姿勢
を取ることで、攻撃の意志や敵意がないこと表していたとされています。
このことは、前社長のコラムの記述と一致しますが、では、握手などが主流である欧米では挨拶についてどのような
解釈がされているのでしょうか。
調べてみると、欧米では、お互いに武器を持っていないことを示すため手段として握手がされていたそうです。国や
文化は違っても、挨拶は「攻撃の意志や敵意がないこと表すため」という目的が共通の背景にあることがわかりま
す。
ともすれば私たちは子供のころから挨拶をすることが当たり前に要求されるなかで、挨拶自体が形式的になったり、
意味を考えなくなったり、時には必要ないと感じてしまったりします。しかしながら、その歴史的背景や意味を理解
し、挨拶の価値を意識したうえで行うと、相手に伝える印象は変わってくるように思います。