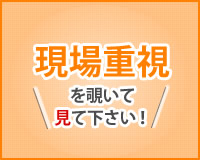2015年12月第三週
第47回:座右の書で学び幸せな人生を送ろう。
明治維新は、当時の幕府に危機感を抱く志士たち、大きな志を持つ若者たちが躍動することで成し遂げられました。
佐藤一斉の「言志四録」は、倒幕の中心となった西郷隆盛をはじめ、佐久間象山及びその門下生として知られる勝海舟、坂本竜馬、吉田松陰、小林虎三郎などに多大な影響を与えた書物としても知られています。
私は、縁あって、今からおよそ四半世紀前に「言志四録」にはじめて接し、その存在価値を知りました。
私は、拾い読みしかしていませんが、私が感動、感銘を受けた言葉について紹介し説明します。
「身恒(みつねに)に病む者は、その痛みを覚えず。心恒に病む者も,亦その痛みを覚えず」即ち「絶えず病気をしているものは、習慣となっているから、痛みになれてしまう。不正な心を持つ者も、良心が麻痺しているから、悪いことをしてもなんとも思わなくなる」。
初めてこの言葉に出会ったとき、なるほど、この表現、ドンぴしゃり言えている!と感心したので、早速覚えたものである。
小泉首相時代の日本を知っている方はご存知だと思いますが、当時の小泉純一郎首相が小林虎三郎の「米俵百俵の話」や「言志四録」の一説をとりあげたことがきっかけとなって、言志四録の「少(わか)くして、学べば壮にして為すことあり。壮にして学べば、即ち老いて衰えず、老いて学べば即ち死して朽ちず」という名言が広く知られるようになりました。
言志四録は、徳川家の大儒学者として君臨した佐藤一斉が記した名著で、中国の古典の「四書五経」(論語,孟子、大学、中庸/礼記、楽記、書教、易経、春秋)を含めて、数多くの古典を引用しながら高い志を持つことの大切さを問うています。
孔子の「天を怨まず、人をとがめず」という言葉を生涯の根本姿勢とし、佐藤一斉は、「我が心、即ち天なり」と表現しています。二宮尊徳も西郷隆盛も、「言志四録」を愛用し座右の銘として人生を送った方です。
昭和の哲学者・思想家の安岡正篤も大いに影響を受けており、儒教の思想は延延脈々と現代に引き継がれてきています。
これと併せて「一燈を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うことなかれ。ただ一燈を頼め」という名言にもよく遭遇します。
偉人の伝記を紐解き、解説している神渡良平は、「佐藤一斉言志四録を読む」の解説本の中で、「私は、命を自覚し、見事な人生を切り開いていった人物たちの伝記を書くことによって、人生をとりこぼさなくてすむ叡智を明らかにしたいと思うようになった。自分の命が見えてくると、次にこれを実現せずにはおかない」という意思、つまり強烈な志が立ってくるとしています。
また、国民教育の父として知られる森信三は、「人間が志を立てるということは、いわばローソクに火を点ずるようなものです。ローソクは、火をつけられると初めて光を放ちます。同様にまた人間は、志を立てて初めてその人の真価が現れるのです。志を立てない人間というものは、いかに才能がある人でも、結局は、酔生夢死の輩(やから)に過ぎないといえます」と述べています。
志を同じくする人どうし、仕事を楽しみ、失敗、困難、苦しみを乗り越えて成果をあげて、喜びを共にしていく仲間がいる職場こそ働き甲斐があるのではないでしょうか。
先人の残した魂の言葉は、人間力を磨いていく金言でもあります。