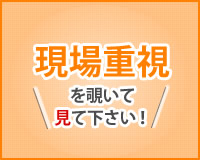2015年12月第二週
第46回:PDCAをまわして幸せな人生を送ろう。
お釈迦様は、古代の原始宗教(自然崇拝、先祖崇拝、多神教崇拝)から脱皮して、道諦(どうたい)の生き方を説いた方です。
そうすることで「苦の原因である煩悩」を消滅させ、悟りの世界を開いた方です。
その教えは、これまでの仏教として日本に伝播し、日本の文明、文化に大きく影響を及ぼしてきました。
西洋では、お釈迦様没後、およそ500年後に、ユダヤ教から脱皮して、キリスト教、そのおよそ500年後にイスラム教が興りました。
宗教論はさておき、日本人の生活に深くしみこんでいる仏教の教えの八正道(はっしょうどう)と予防処置の関連性・共通点について考え、理解することにしましょう。
八正道(はっしょうどう)とは、
①正業(正しい行い、仕事をしましょう。恥ずかしくない仕事に従事しましょう)、
②正語(正しい言葉を使いましょう。毒舌はやめましょう)、
③正思推(正しく考えましょう。人間として何が正しいか考えましょう)
④正見(正しく物事を見ましょう。真理を見抜く力を備えましょう)
⑤正念(邪念を離れて正しい道に専念しましょう)
⑥正精進(正しい目的に向かって精進しましょう。再発防止対策)
⑦正命(清浄な生活をしましょう。予防処置)
⑧正定(正しく実践していきましょう。八正道を実践しましょう。言行一致の世界です。)
日本人は、正月を迎えるに当たって、除夜の鐘を聞き、煩悩をなくして新しい信念を迎えることを慣わしとしています。
これは全て仏教の考え方からきています。煩悩は108あるといわれています。
なぜ108か?108の煩悩はどんなものか?それを明確にし、なくしていくのが「苦集滅道(くしゅうめつどう)」であることは前回の勉強会の「四諦」で取り上げましたので記憶にあると思います。
さて、108の煩悩とは一体どこから来ているのでしょうか?少々言葉遊びになりますが、四苦とは人間であれば誰もが避けては通れない「生・老・病・死」、八苦とは、それに精神的な苦悩「愛別離苦」(あいべつりく)「怨憎会苦」(おんぞうえく)「求不得苦」(ぐふとくく)「五蘊盛苦」(ごうんじょうく)を加えていいます。
四苦八苦を掛け算して加算すると(36+72=108)となり、108種の煩悩が存在するとの所以です。
調べてみると日本語の成句、造語は、言葉遊び、語呂合わせとなっているケースは意外と多いことがわかりました。
今から、2500年前、孔子の弟子である曹子(ソウシ)の「われ一日に三度わが身を振り返る」に由来する「三省」という表現があります。
人生の成功者となるかどうかは自分自身を管理する、すなわち今風に言えば、自己の人生でPDCAをまわすことであります。
内面的にこのPDCAを絶えずまわすことは至難の業でありますが、多くの先達の成功者は、自分を律して、努力し、人生でも反省を繰り返して人生の目標を達成しています。
人生の成功者となるかどうかは自分自身を管理する、すなわち今風に言えば、自己の人生でPDCAをまわすことであるといっても過言ではありません。
私たちが生業とするISOマネジメントシステムでもこのような考え方が基本になっていることが理解できると思います。